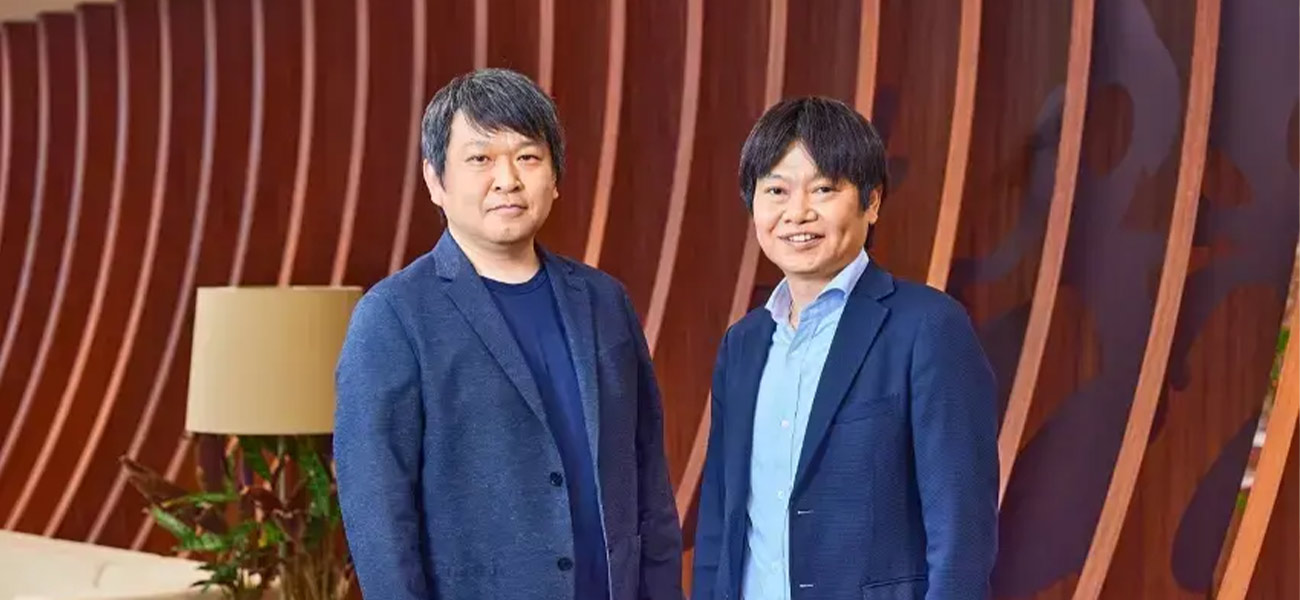「世界を見据えたゲーム開発」セガ第4事業部が挑む、
これまで数々のヒットゲームを⽣み出してきたセガ。世界中で愛され続けるIPを活かし、グローバルのモバイルゲーム市場で新たな価値を創り出しているのが第4事業部です。
モバイルゲームを戦略の軸に据え、⽇本発のコンテンツを世界へ届ける。その最前線で活躍するのが、2025年4⽉に副事業部⻑に就任した久井克也⽒と⼩菅慎吾⽒。⼈気タイトルの成功を支えてきたおふたりに、グローバルに通⽤するゲームづくりの裏側と、若⼿・中途を問わず活躍できる組織づくりについて伺いました。
モバイル開発の第一線を歩んできた二人のキャリア
まずはお二人のキャリアについて聞かせてください。
久井
私は2008年に新卒でセガに入社しました。最初は『プロサッカークラブをつくろう!(以下サカつく)』などのコンシューマタイトルを作っている部署で、プランナーからスタートしています。そこからモバイルへとシフトし、「セガネットワークス」が分社化されたタイミングから10年ほど在籍しました。
その後、セガに戻ってきて、今期から第4事業部の副事業部長を務めています。現在管掌しているチームはセガネットワークス時代の流れをくむものが多く、私自身も長年モバイル開発に関わってきました。
小菅
私は2017年にセガに中途で入社しました。前職もコンシューマ系の大手ゲーム会社で、プロデューサーとして長らくゲーム業界で働いています。セガへの入社以降はモバイル領域を中心に活動しています。転職を決めたのは、大企業なのにやりたいことにチャレンジできるマインドを感じたからです。
入社してすぐ『プロジェクトセカイ(以下プロセカ)』を立ち上げプロデューサーとIPオーナーを兼任しています。今期からは本事業部の副事業部長と、プロデューサーが集まる「プロデュース部」の部長も務めています。
第4事業部とは、どのような組織なのですか?
久井
もともとはモバイル領域、F2P(Free to Play)モデルが得意な組織なので、そこをベースにしつつ、世界中のより多くの方に届けられるように“マルチデバイス”でゲーム開発をする組織です。また、“ゲーム体験をしっかり作る”をミッションにしています。世の中には数多くのゲームが存在しますが、中にはゲームシステムを変えずIPを変えただけのものも少なくありません。もちろん、私たちもそれで成功してきた実績がありますが、市場が成熟するにつれ通用しなくなってきています。改めて、本質的にゲーム作りに向き合うのが第4事業部だと思っています。
小菅
ゲーム作りで意識しているのは「自分たちが面白いと思うもの」だけではなく、「ユーザーが面白いと思う体験とは何か」を徹底的に突き詰めること、それができる組織にしようとしています。質の高いゲームとして、サービスとして、どう展開していくかという視点が欠かせません。
特に私たちは、グローバルで長期にわたって楽しんでもらえるゲーム作りも目指しているので、海外のユーザーのゲーム体験にも本気で向き合っています。
「ユーザーと一緒にゲームを育てる」開発中から続く対話型アップデート体制
具体的に、どういったタイトルを中心に開発しているのでしょう。
久井
最近は、新作タイトルの開発も進めています。たとえば『サカつく』の新作は、僕自身がプロデューサーとして見ているプロジェクトです。そこで大事にしているのは「そのIPのファンがどんな体験を求めているか、期待しているのか」を丁寧に考え抜くこと。
今回の『サカつく』は、ビジネスモデルこそF2Pですが、体験設計としては、かつてコンシューマゲームで遊ばれていた頃の“あの感覚”を再現することを意識しています。過去作を遊んでいた方が触れた時に「ああ、これがサカつくだよね」と感じてもらえるような体験に仕上げたい。そういう意味では、IPファンと真剣に向き合う作り方をしています。
リリース前からユーザーと向き合い続けるのですね。
久井
そうです。新作情報の発表後は、X(旧Twitter)などを通じてユーザーの声を積極的に拾いながら、「一緒に作っていこう」という姿勢で開発を続けています。F2Pモデルには、コンシューマゲームとは異なるビジネス上の制約や特性があるんです。たとえば「ここができないとサカつくじゃない」と言われるような機能が、ビジネス的に成立しない場合もある。そのバランスをどうとるかは、常に悩みどころでもあります。
そのため、運営組織(オンラインモバイルパブリッシング本部)とも密に連携しています。彼らの知見を活かしながら、「ビジネスとしてスケールさせるにはどんな機能が必要か」といった観点も加えて、チームで調整しています。そこは本当に大変ですけど、やりがいも大きい部分ですね。
なぜユーザーの声により向き合うべきだと感じるようになったのでしょうか?
小菅
これまでセガは挑戦を続けてきたのですが、思うような結果が出ない状況が続いたときに、「今までと同じやり方ではダメだ」と痛感したんです。
そんなときに、強い刺激を受けたのが、一緒にタイトル開発している企業様の姿勢でした。彼らは本当にユーザー視点を徹底していて、驚くほど良いものを作り続けている。僕自身、もともとそういう“面白いゲームを真摯に作る”というマインドでこの業界に入ったのに、いつの間にかそれを貫くのが難しくなっていたんです。彼らの取り組みを間近で見て、「もう一度そこに立ち返ろう」と強く思いました。結局、みんなゲームを作ることが好きだから、このやり方ができるはずだと思っています。
マルチデバイス×グローバル展開を見据えた“セガならでは”のアプローチ
グローバル展開をするうえで意識している点を聞かせてください
小菅
グローバル化した昨今は日本で作ったゲームをそのまま出せば受け入れられる、という時代ではありません。プレイスタイルや文化、商品購入に対する感覚も国によって全然違うので、それぞれの国や地域のユーザーが“違和感なく遊べるかどうか”を常に意識しています。
ちょっとしたことでも良くて、たとえば「アメリカの子供たちって何をしている時が楽しいのかな?」と日常をイメージすること。もちろん、日本とは違う部分もありますが、共通する部分も多いです。グローバルだからといってビビらず、世界のユーザーに向き合いながらカルチャライズを研究し続けることが重要です。
マルチデバイスはどのように進めているのでしょうか?
久井
どのような企画もマルチデバイスでつくることを基本として考えています。すでにモバイルでリリースしたタイトルでも運営中にPC対応をした実績もあります。モバイルだけでなく、PCやプレイステーションなどで展開することで、カジュアルに遊びたい人から、トップオブトップを目指すような人まで、同じ環境で遊んでいただけるようになります。対戦アクションゲームなどでデバイスによって有利不利が気になる方はマッチングの設定ができるようにするなど、タイトルを展開しながら、分析と研究を重ね、ユーザーが求める形を模索しています。
第4事業部として特に強みを発揮できるのはどういったジャンルなのでしょうか?
久井
まずは「マルチアクション系」ですね。たとえば我々が開発している『SONIC RUMBLE』のようなジャンルです。アクション性が高く、複数人で同時に遊べるようなタイプのゲームですね。
セガのゲームに触れたことがある方なら分かると思うんですが、動かしたときの“手触り”がとても良いんです。『ソニック』シリーズをはじめ、キャラクターの操作レスポンスの良さやアクションの気持ちよさは、セガの伝統とも言える強みだと思います。これは他にはなかなか真似できない部分だと感じています。
小菅
忘れてはいけないのが「コミュニティ」の部分です。ユーザーと向き合う開発を目指しているからこそ、ゲーム内のコミュニティづくりにも非常に力を入れています。ギルドやチャット、グループバトルなどのゲーム機能は勿論、ゲーム外のコミュニティも含めたトータルでプレイヤー同士のつながりを重視する設計は、セガらしさが詰まっていると思います。
こうした“ユーザーとのつながりを大切にしたゲーム作り”こそが、私たちの最大の強みだと思います。
海外スタジオとの連携から見えた、日本式開発の価値と可能性
近年は中国のゲーム会社の成長も著しいですが、他社の取り組みを参考にすることもあるのでしょうか?
小菅
ありますが、盲目的に追従するわけではなく、自分たちが得意な領域を見つめ直し、それを軸に戦っていこうという方針で進めています。たとえば「ここはすでに競争が激化しているから別のアプローチでいこう」といった具合に、市場全体を見渡しながらポートフォリオを組み直しているところです。
実際に海外のゲーム社と連携した実績もあるのでしょうか?
小菅
『アングリーバード』で知られるフィンランドのゲーム会社、ロビオ・エンターテインメントをセガグループに迎え、一緒に開発を進めているタイトルもあります。とはいえ、全てを海外のやり方にしたからといってうまくいくとは思っていません。
法制度や働き方の違い、国民性や意思決定プロセスも異なる中で、日本ならではの「丁寧にゲームを作り、皆で議論しながら確実に進めていく」やり方には大きな価値があります。時間はかかるかもしれませんが、それが日本の強みだと考えています。
一方で、ロビオの開発スタイルから学ぶこともあったと。
久井
そうですね。欧州スタジオでは、リリース前に入念にテストを重ね、結果を見ながら改善を繰り返すという文化があります。コンテンツの“勝算”が見込めなければ、一度引いて撤退するという判断もごく自然に行われています。
これは日本のゲーム会社ではあまり見られなかったスタイルで、我々も全部が全部その手法を採用するわけではありませんが、プロジェクトによっては実際にそうした取り組みも始めています。
「作る側も、見る側も」AIが変えるゲーム体験の最前線
技術向上の一環として、どのようなAI活用に取り組んでいますか?
久井
AIに関しては、私達の事業部においてもさまざまな取り組みを行っています。すでに製品に組み込んでいる機能もありますし、技術研究を進めている段階のものも複数あります。
たとえば、効率化の面では、3Dキャラクターのモデリング生成がそうです。今作では非常に多くの架空のサッカー選手の3Dモデルが必要なのですが、手作業の制作だとかなり時間がかかります。そこにAIの自動生成を導入することで、大量のキャラクターを効率よく作れるようになっており、昨年あたりから製品レベルでも実現可能性が見えてきています。
開発支援だけでなく、ゲーム内でのAI活用も進んでいるのでしょうか?
久井
はい。たとえば、今研究中なのが「ゲーム内実況」のAI化です。セガが得意とするマルチアクション系のバトルゲームでは、実際にプレイするだけでなく、観戦する側のユーザー体験も重要になってきています。
ただ現状では、観戦者が十分に楽しめているかというと、そうとは言い切れません。たとえば「今、どこで何が起きているのか」などをリアルタイムに解説してくれる実況があると、観戦の楽しさは格段に向上するはずです。ここにAI実況を導入できないかと考えています。実現にはまだ課題も多いですが、ある程度の目処は立ちつつあります。
社内業務支援としてのAIと、ユーザー向け機能としてのAI、両面での活用が進んでいるのですね。
久井
特に後者、ユーザー体験に直結する部分でのAI活用には、より力を入れていきたいと考えています。とはいえ、現状ではAIが万能というわけではありません。技術的にまだ実現が難しい部分も多く、ゲームとして本当に面白いものを成立させるための“バランス”には常に悩まされています。また生成AIの受け入れられ方は地域によっても温度差があります。グローバルに展開する事業が多い分、このあたりにも非常に気を遣っています。
“創造は生命”を体現する──自分の意思で動ける人が輝けるチーム
どんな人がセガにマッチすると思いますか?
久井
セガはとても柔軟な会社だと思うので、自分の意志を持って動ける方は楽しめると思います。いろんな考え方を受け入れてくれる土壌があって、自分なりにここまでやってこられたのは、その懐の深さがあったからだと感じています。
ちゃんと“意思”があれば、それを伝えることができる環境ですし、変に我慢して上の指示だけをこなすような空気はありません。自分の意見を交わしながら、チームで考え、動いていける――そんな強さがある人の方が、きっと楽しめると思います。
あとはやっぱり、「創造は生命」という言葉に象徴されるように、ものづくりにしっかりコミットできる環境なんです。作るものに本気で向き合いたい、そんな人にとっては本当に幸せな場所だと思いますね。
意思を持って手を挙げれば、チャンスがもらえますか?
久井
そうですね。企画コンペは頻繁に開催されていますし、「こういうネタで何か考えられないか」「このIPで何かできないか」といった企画募集もよくあります。そういう時に自分から提案を出せる姿勢があれば、デザイナーやプログラマなど職種関係なく、チャンスをつかめる環境です。
小菅
昨今のゲームは開発規模が大きいので「みんなで作る」ものです。だからこそ、他者と協力しながら進めることを楽しめる人や、周囲に良い影響を与えられる人は、どんどん伸びていくと思います。会社全体として、みんなにチャンスがあるので、他者を尊重できる人が合うんじゃないかな。また、作るゲームの領域が広く、グループのアニメ会社や映像会社など多様な業態と関われるのは、セガならでは。モバイルに限定せず色々なことに挑戦したい人はセガに向いていると思います。
海外駐在も夢じゃない──開発職にも開かれたグローバルチャレンジ
入社してからは具体的にどのようなキャリアを描けるのでしょうか?
久井
私たちの事業部では明確なキャリアパスを職種ごとに定めています。たとえば、プランナーといっても「レベルデザイン」や「ゲームデザイン」などさまざまな分野があり、それぞれの方向性を明文化して、社員が目指すゴールを定めやすくしています。
マネージャーとの面談を通じて、「自分はこういうスキルを伸ばしたい」「将来こういう立場を目指したい」といった目標を話し合いながら、個々にあわせたキャリア設計を行っています。もちろん途中で方向転換も可能ですし、プロデューサー・プランナー・デザイナー・プログラマのいずれも同じように支援しています。
小菅
中途で入った方も基本的には同じですが、今までの経験がすぐに活きたアサインになります。
久井
また、昨今は初期開発だけでも少なくとも2年、長ければ4、5年かかります。運営が始まるとエンドレスになってしまうこともあり、同じプロジェクトに長期間配置され続けてしまうという課題も生じていました。ですので、特に若手社員や、運営中プロジェクトにアサインされた社員は一定期間で配置転換をおこなうなどのルールを設け、社員が自らのキャリアや技術の幅を広げ、伸ばしやすい環境を整備しています。
グローバルにも自由に挑戦できるものなのでしょうか?
久井
まず、私たちが管掌しているプロジェクトは日本のスタジオを中心に開発をしています。そのため「海外をメインとしたタイトルをつくる」というよりは、日本でつくったプロダクトをどう海外に届けるか、という視点で関わることになります。
一方で、「海外で働く」という意味では、実際にアメリカ(ロサンゼルス)やヨーロッパ(ロンドン)のブランチに駐在するチャンスがあります。事業部内で公募をかけ、「やってみたい」という人を募った上で、選考や面談を経て派遣されています。すでに何人もそういったかたちで海外に赴任しています。
最後に、セガに興味を持った方へのメッセージをお願いします。
小菅
最近は「モバイルゲームは厳しいよね」と言われることも多いのですが、僕らは全く悲観していません。事実、日本のゲーム会社からも面白いタイトルがたくさん出ていますし、当然セガも新しく面白い作品を作る努力をしています。
モバイルゲームの市場はまだまだ大きいです。グローバル展開も視野に入れつつ、「目の前のユーザーに面白いものを届ける」という気持ちで、細部までこだわれるのがセガの強さ。諦めずに挑戦したい人には、うってつけの場所だと思います。ぜひ一緒にがんばりましょう。
久井
私は、技術や知識をどん欲に吸収したい人と働きたいと思っています。第4事業部は基礎研究にも力を入れていて、AI研究や他事業部との技術交流など、学びの場がとても多い。自分を成長させたい人には本当にいい環境です。
特にプランナーやプロデューサーなら、ゲームをたくさん遊んでいることは前提になりますが、それに加えて「自分の得意領域」を持っていると強い。例えそれが狭くても人より深く掘り下げているなら武器になります。職種関係なく、そういうバックグラウンドを開発に生かせるのが、セガの良さだと思います。